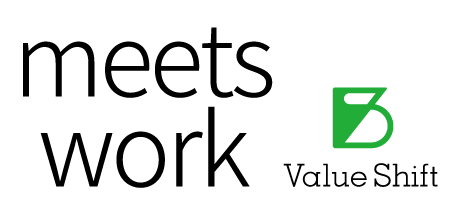「終身雇用」とは
日本では一度雇った社員を定年(※1)まで長期的に雇用する方針や慣習が一般的です。
企業に採用される際は、特定のプロジェクトや特定の仕事だけを期待されているのではなく、企業全体への貢献を期待されていますので、「就職」より「就社」という表現がしっくりくるかもしれません。日系企業で働く外国人から見ると、日本人には転職を経験している人が少ないという印象を持つのではないでしょうか。
日本人は入社する時に「定年までこの会社で働く」ことを前提と考えている人が多くいます。雇用が保証されているため、就職企業に対して強い信頼を感じているのです。この絆のもと「この会社のために一生懸命働く」という意識を社員に持ってもらうことが、終身雇用における企業のメリットと言えるでしょう。
逆に、終身雇用は定年までの雇用が保証されているため、「必要以上に頑張らなくても働き続けられる」といった意識で、長く在籍しているのに成長するための努力を持たない社員が出てくる可能性も否定できないというところはデメリットでもあります。
(※1) 社員が一定の年齢に達すると自動的に雇用関係が終了する制度を「定年制」という。日本では60歳や65歳を定年と定めている企業が多くある。
「年功序列」とは
年功序列とは、業務の成果より「勤続年数」や「年齢」といった要素を重要視して役職や賃金を決める慣習や人事制度のことをいいます。
つまり、職務に対する報酬ではなく労働年数に対する報酬になっているということです。社員の賃金は、企業が定めた初任給から始まって勤続年数が長くなるにつれ徐々に上がっていきます。
例えば、大きな成果を出したり、スキルアップしたからといってすぐに賃金がUPするわけではありません。同じような仕事の成果・評価であっても、「あの人と賃金が同じじゃない」「自分の賃金は上がっていない」という状況があり得るのです。
若い社員の賃金は低いですが年齢と共に徐々に賃金が上がっていきますので、仮に20年後その社員の生産性が落ちていたとしても、勤続年数に伴って若い頃より賃金は上がっていくわけです。転職して新しい企業に入社するより、一つの会社で長く働く方が高い賃金を受けることができる仕組みになっています。
この年功序列の仕組みは、社員が就職した会社で長く働き続ける強い動機になり、人材の長期的な育成を可能にします。そしてベテラン社員の在籍が、ノウハウ蓄積や若手育成につながるというメリットがあります。一方で、成果が賃金に反映されにくい若者にとっては不満を感じるというデメリットもあるでしょう。
変わりつつある日系企業
伝統的な「終身雇用」と「年功序列」ですが、企業においても、求職者においても意識が変わりつつあります。
最近の日本の若者の中では、同じ会社で定年まで働くというより2、3年で職を変えながらスキルアップしていきたいという考えが増えてきています。それに伴い自分のスキルや成果を正当に評価してもらえる企業を求めています。
近年はIT技術やテクノロジーの発展によって人がおこなう業務内容が年々変化しています。一つの企業で長期間かけて蓄積してきた知識やノウハウなどに大きな価値がなくなっている例も増えているでしょう。かつてのように経験を積み重ねてきたベテラン社員こそが活躍し、成果を出しているという状況ではなくなってきています。
時代にそぐわなくなってきた年功序列による人事評価制度を見直していく企業も増えています。従来の「どれだけ長く働いたのか」で評価される仕組みから、成果や目標達成、個々の強みを評価し、年齢や勤続年数に左右されず実力を発揮できる環境を実現させる日系企業も増えていくのではないでしょうか。
また、有望な社員に長く勤めてもらうために、一人一人のスキルを中長期的に向上させていくための「キャリア開発」に取り組んでいる企業もあります。自社内でどのようなキャリアパスを描けるのか、また目指すキャリアに到達するためにはどのような経験を積み、スキルを身に付けるのか、社員が将来の目標に向けて意欲的に業務に取り組めるような環境を工夫して、人事制度を整える企業も増えてきています。